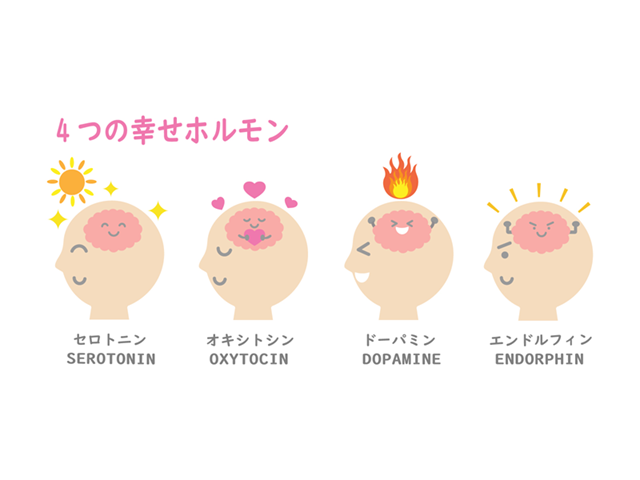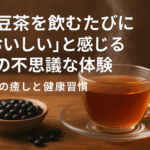「最近、なんだか気分が落ち込むなあ…」
そんな風に感じるとき、私たちの心と体のバランスを整えるカギとなるのが「幸せホルモン」です。
名前は聞いたことがあっても、具体的にどんな種類があり、どうすれば分泌されるのかまで知っている方は
少ないかもしれません。
この記事では、私たちの幸福感に大きく関わる4つのホルモンと、それを日常生活の中で増やす方法について、
わかりやすくご紹介します。
目次
幸せホルモンとは?
「幸せホルモン」とは、心の安定、愛情、やる気、満足感といったポジティブな感情を生み出す神経伝達物質
の総称です。
科学的にはホルモンというよりも「脳内物質(神経伝達物質)」ですが、私たちが「幸せ」を感じる要因として
広く知られるようになりました。
主に以下の4種類があり、それぞれ異なる働きを持っています。
• セロトニン(心の安定ホルモン)
• エンドルフィン(快感ホルモン)
• ドーパミン(やる気ホルモン)
• オキシトシン(愛情ホルモン)
4つの幸せホルモンとその働き

セロトニン:「心の安定ホルモン」
セロトニンは、感情のコントロール、睡眠の質、集中力などに大きく関わるホルモンです。
ストレスを感じやすい現代社会では不足しがちといわれています。
分泌を促す習慣:
• 朝日を浴びる
• リズム運動(ウォーキングや深呼吸)
• 発酵食品(納豆、ヨーグルト、味噌)を摂る
特に朝の散歩や呼吸法は、心を落ち着けるのに効果的です。
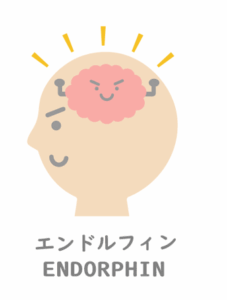
エンドルフィン:「快感ホルモン」
エンドルフィンは、痛みを和らげ、多幸感やリラックスをもたらすホルモンです。
「ランナーズハイ」と呼ばれる現象も、このエンドルフィンの分泌によるものです。
分泌を促す習慣:
• 笑うこと
• 音楽を聴く
• 感動する映画を観る
• 運動(特にランニング)
自然な抗うつ作用があるとも言われており、気分が落ち込みがちなときには特に意識したいホルモンです。

ドーパミン:「やる気ホルモン」
ドーパミンは、報酬系と呼ばれる脳の働きに関わるホルモンで、「達成感」や「快楽」を感じる源です。
モチベーションアップに大きな影響を与えます。
分泌を促す習慣:
• 小さな目標を立てて達成する
• 趣味や好きなことに没頭する
• チャレンジ精神を持つ
ただし、強すぎる刺激や依存(ギャンブルやSNSなど)には注意が必要です。

オキシトシン:「愛情ホルモン」
人とのつながりや信頼を深めるときに分泌されるオキシトシンは、「絆」や「安心感」を育てるホルモンです。
分泌を促す習慣:
• ハグや握手などのスキンシップ
• ペットと触れ合う
• 「ありがとう」「大好き」といった言葉を交わす
• 人との温かい交流
孤独感の軽減やストレス緩和にも効果があり、心の健康を保つ上で欠かせない存在です。
幸せホルモンを増やす生活習慣
誰でも簡単にできる、幸せホルモンを活性化する行動を以下にまとめました。
| 行動 | 主に増えるホルモン |
| 朝日を浴びて軽く散歩する | セロトニン |
| 感動する映画を観る | エンドルフィン・オキシトシン |
| 小さな目標を達成する | ドーパミン |
| 「ありがとう」を伝える | オキシトシン |
| リズム運動(深呼吸・ウォーキング) | セロトニン |
| ペットと触れ合う | オキシトシン・セロトニン |
| 趣味に没頭する時間をつくる | ドーパミン |
無理をせず、楽しみながら続けられるものを1つでも取り入れることが、毎日の気分を少しずつ変えていきます。
毎日の中に無理なく取り入れ、少しずつ心の土台を整えていきましょう。
まとめ:幸せは、自分で育てられる
「幸せホルモン」は、特別な人や大きな成功がなくても、日常の中で自分自身の行動によって分泌を促すことができます。
朝の光を浴びる。
好きな音楽を聴く。
誰かに「ありがとう」と伝える。
そんな小さな一歩が、脳と心に穏やかな変化をもたらしてくれるのです。
今日できることから、あなた自身の「幸せ」を育てていきませんか?